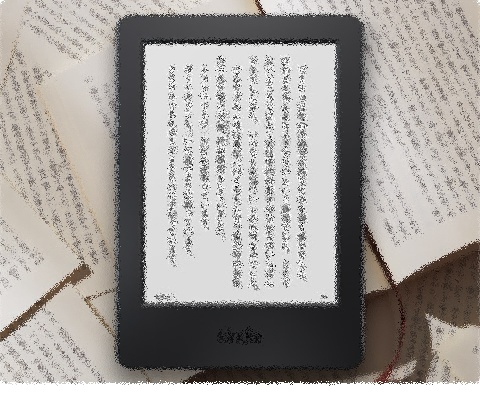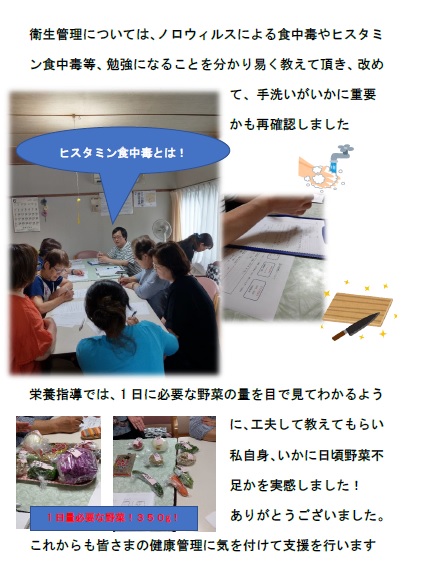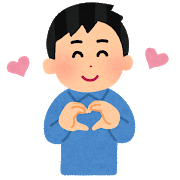あけましておめでとうございます(^_^)v
2020.01.06
みなさん、こんにちは(*’ω’*)
グループホームちろりん担当者です☆
新しい年を迎えて、1週間が経とうとしていますね。
今日は内村病院のグループホームの世話人さんが腕によりをかけて作ってくれた『おせち』を紹介します。
毎年とても手の込んだおせちを作ってくれ、入所している方たちからも「美味しい!」ととても評判が良いです(^_^)v
そして、これが2カ所のグループホームの『おせち』です(´艸`*)![]()
↓ ↓ ↓
本当、素晴らしいですよね(*’ω’*)パチパチ‼
私も世話人さんを見習って、季節の行事食や健康を考えた食事を作っていこうと思います。
それでは、みなさん☆
まだまだ寒い日が続くので、体調に気を付けて今年1年も元気に過ごしましょうね(*^^)v
今年もあとわずか(*^^)v
2019.12.23
こんにちは!!
6年目の精神保健福祉士です(*’ω’*)
早いもので令和元年が終わろうとしています。
皆さんはどんな1年だったでしょうか???
私はあっという間の1年だったような気がします。
振り返ってみると昨年の今頃に「たまには日記をつけてみませんか?」というブログを書いていました。
ブログを書いたことはすっかり忘れていましたが日記は続けていますφ(..)カキカキ
さて、
内村病院で今年変わったことといえばなんだと思いますか?
それは・・・制服です(´艸`*)
以前はこんな制服でしたが覚えていますか?
ちなみに写真はいつも頼りにしている先輩にお願いして撮影しました(´艸`*)![]()
そして、今は・・・
始めは制服の色やポケットの大きさが違うなーと違和感がありましたが
今ではすっかり慣れて着こなしています(笑)
心理士さんたちと同じ制服なので時々間違われることもあります。
来年も良いことは継続しつつ、新しいことにチャレンジできる年にしたいです(*^^)v
電子書籍
2019.11.05
こんにちは(*’ω’*)4年目の精神保健福祉士です♪
夏も終わり少しずつ寒くなってきましたね!!
早速ですが、みなさんは『読書』はお好きですか??
私は読書といっても小説など長い文章を読むのは苦手です(^-^;
どちらかというと『漫画』を読みます♪♪
最近では紙媒体の書籍より『電子書籍』で読む人も増えているようです!!
私も去年『キ〇ドル』という電子端末を購入してからは電子書籍を購入するようになりました(*^^)v
電子書籍にした理由は、紙媒体だと何十巻もある漫画を持ち歩けませんが、電子書籍だと端末さえあればどこでも漫画を読むことができます(*^▽^*)。外出先での待ち時間やちょっとした時に気軽に読むことができるので便利だなと思います(タブレットやスマホでもアプリをダウンロードして電子書籍を購入できます)。
もう1つは漫画を購入する際、本屋さんに行かずとも近くのコンビニやネットでお金を支払って購入できるので助かります!
読書もいろんな形で楽しめるようになりましたね!
みなさんも『読書の秋』を満喫してください(*^^)v
PSW平成見聞録~序章~
2019.10.24
こんにちは!
毎回ブログのネタ探しが憂うつな古参の精神保健福祉士です。
今年、元号が「令和」に変わり、新しい時代を迎えました。
私が学生(昭和)の頃は、「福祉職」は一般的には障害者福祉(児童・障害者施設の指導員)のイメージが強く、国家資格もなく、PSW(精神科ソーシャルワーカー)という存在は全くと言っていいほど知られていませんでした。
それなのになぜこの職を選び、自分が今ここにあるのか…新しい時代に入り改めて考えると感慨深いものがあります。
なぜ「福祉」という進路を選んだのか…、今思うと昭和53年「24時間テレビ~愛は地球を救う~」が始まり、昭和54年国際児童年で連日のようにTVからゴダイゴの「ビューティフルネーム」が流れ、アフリカ飢餓難民を救うための「We Are The World」「LIVE AID」が世を賑わせ、純真無垢かつミーハーだった私は、メディアを通しての「チャリティー精神」に単純に感化されたのかもしれません。
将来の進路に迷っていた時期に「人のためになる仕事をしたい」という大義名分を見つけ、
当時少なかった福祉系大学に進学したのが始まりだったような気がします。
私が精神科病院のPSWとして就職した昭和63年は、精神科医療において「精神衛生法」から「精神保健法」への大改正を遂げた歴史的年でした。新卒で精神科病院や精神障害者がいかなるものかを全くと言っていいほど知らないまま現場に投げ込まれ…あれから31年。一言では語りつくせないほどいろいろありました。
平成時代は、「福祉」の激動期と言っても過言ではありません。介護保険、障害者基本法、成年後見制度、医療観察法等々、書ききれないほどの法制度が制定・改正され、「福祉」が医療・司法・教育・労働等々、様々な分野と協働する様になりました。「福祉」と言う言葉があちこちで使われ、専門職の需要も増え、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の国家資格もでき、福祉系大学や専門学校もびっくりするほど増えました。
新法により今までの常識が変わり、今までなかったことが新規事業として始まり、それらを当たり前のように定着させていく大変さは、テキストの一文だけでは伝わる物ではありません。昔話は流行りませんが、事実は小説よりも奇なりです。私が体験した「平成の福祉の現場」を機会があれば小出しにアップしたいと思います。
今回はその序章と言うことで、続きはまた次回に…。
終戦から74年...
2019.08.15
みなさま、こんにちは。 地域医療連携課の精神保健福祉士です。
今回は真面目な話をします。
今日は、『終戦記念日』です。
もう、戦争は70年以上前の話になりました。
「もう、70年以上前」とは、恐らく戦後生まれ(この言葉も死語となりつつある
ようです)の私たちの感覚だと思います。
体験された方は、いつまでも“その時代”を忘れないと思いますし、国によっても感覚
が違うと思います...
実際、隣国とは、未だにそのことで揉めていますものね。
私も、子供の頃や若い頃は、学校で聞く「せんそうの話」や親戚の伯父さんや祖父母が
話してくる「せんそうの話」は、正直「・・・また、その話・・」と聞く気が全くあり
ませんでした。
面白くなかったです。
嫌だったです。
しかし、自分が、年齢や経験を重ねるにつれて変化が生じました。
今なら、親戚の伯父さんたちや祖父母にもっと聞いてみたい事がたくさんありますが
もう、叶いません。少し前までは、入院されていた患者さんから教えてもらったりし
ていましたがそんな方達も少なくなって参りました。
私の母親は認知症ですが、当時、半島に居た時のことは覚えており、「日本が負けた
日には、町中で爆竹が鳴って喜んでいた」「引き上げ船では、死んだ子供、或いは
新生児は、生きたまま海に投げ捨てられていた」と話します。
そして、必ず最後は「戦争はいかん。戦争をすると惨めだ」と締めくくります。
いくら本やメディアから情報として取り入れても、こんな風に、実体験をした方々の
口から聞く話のようには、心に染みわたりません。
どうか、皆さんも、周りにまだその話が出来る方がおられるのであれば、終戦記念日
には色々教えてもらって下さい。
後世に受け継がなくてはならない大切な話だと思います。
高校野球!! そんな私が応援しました\(^o^)/
2019.08.13
新米の精神保健福祉士です☆
2019.07.22
はじめまして!
新米の精神保健福祉士です(*^^)v
4月に入職し、もうすぐ4ヶ月。ようやく少し慣れてきたところです。
今日は自己紹介をさせていただきたいと思います![]()
小林は地元です。もうずっと市外に住んでいましたが、久しぶりに小林に戻ってきました。
新米と言いながら年齢的にはあまり初々しくありません・・・笑
前職は保育士で、障がいのある子どもさんの施設や小児科病棟などに勤務していました。
精神科病院で働くのは初めてで、もちろん精神保健福祉士としての仕事も初めてです。なので、新しいことをひとつひとつ先輩方から教えていただいています。
うっかり、のんびり、あわてんぼうの私ですが、まだまだ始まったばかりなので、焦らずに覚えていきたいと思いまo(^o^)o
そして、好きな食べ物はピザです(^_^)/たっぷりチーズをのせてタバスコをかけて食べるのが好きです。
それからお野菜![]() 無農薬だったらすごく嬉しいです。今の季節は朝食でスムージーを作ったりします。
無農薬だったらすごく嬉しいです。今の季節は朝食でスムージーを作ったりします。
ちなみに料理はあまり好きではありませんが、必要に迫られて日々やっています。子どもがいるので時短レシピが助かります。簡単でおいしいメニューありましたらぜひ教えてくださいね(^_-)-☆
これからどうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m
グループホーム 『チロリン』 です。
2019.06.28
☆多肉植物の寄せ植え☆
2019.06.24
こんにちは!6年目の精神保健福祉士です(*^^)v
令和になりあっという間に2ヶ月がすぎ、ようやく書類に令和とスムーズにかけるようになってきました( ..)φ
令和初!!なんてよく聞きますが、私も令和になって初めてチャレンジしたことがあります。それは・・・「多肉植物の寄せ植え」です!!
おしゃれ女子の間で流行っていると聞きつけ(数年前から流行っていたようですが・・・)ネットで調べて土や肥料、鉢植えを買ってトライしてみました!
そもそも多肉植物とは葉や茎、根に水分をためられる多肉質の植物の総称だそうです。南アフリカや南米など雨の少ない地域が主な原産地で極度に乾燥した環境や塩分の多い土地で生き抜くために適応して、ぷくぷくとした葉っぱや茎になったようです。ちなみにぷくぷくというよりつんつんしているサボテンも多肉植物の仲間だそうです。
多肉植物や鉢植えもいろいろと種類があって、どれにしようかと悩んだ末に完成したのがこちらです。
自分で植えたからこそ愛着がわき、今は毎日水をあげることが習慣になっています。
植物に癒されるな~と改めて思い、次は食べられるものにチャレンジしてみようかと考えています。
皆さんも疲れた時には植物で癒されてはいかがでしょうか?
↓↓ちなみにこれは友達の寄せ植えです。
最後に少しだけ・・・
先日、職場で何気なく「◌◌◌のポイントシールを集めて今欲しい商品をGETしようと思ってるんですよ~!」と口にした私(*^_^*)
すると・・・翌日から次々に「これ集めてるんだってね~」と職場のみんながポイントシールを持ってきてくれました!そして、わずか数日で目標達成!!
まさか、こんなに早く集まるとは思っていなかったので、びっくり\(◎o◎)/!!
ポイントシールを通して、みんなの優しさを感じ、改めて良い職場だなぁと思った今日この頃です( ^^) _旦~~
職場の後輩 ~8年目精神保健福祉士のつぶやき~
2019.04.30
みなさん、こんにちは!
4月で8年目を迎えた精神保健福祉士です(*^^)v
今日は私の後輩について話をしたいと思います。
私には3人の後輩がいます。
1人はまだ入職したばかりですが、残りの2人は今年で4年目、6年目を迎えます。
今日は入職して4年目、6年目の後輩について話をしたいと思います(^_^)/
まずは4年目の後輩です。
新卒で入職してきた彼は入職時よりおっとりしていて、癒し系キャラ。
存在だけで人を癒せるなんてすごいなぁ~なんて思っていました。
4年経ってもそれは変わりません(*^^)v
でも、この4年間で彼は少しずつ経験を積み重ね、「出来る男!」に成長しました!
普段は優しい彼ですが、いざという時はしっかり相手に「NO!」を言えるようになりました。
自信がないと質問が多かったように思いましたが、今では自分でしっかり判断して行動する事ができます(^_-)-☆
ひと月にこなす書類の量や電話の数が今までより増えた気がします!
そして、最近では周囲の些細な変化にいち早く気づき「素敵ですね!」「変わりましたね!」と言葉をかけてくれるようになりました。その一言でとても気分が良くなります♪♪
この4年間で彼なりにたくさんのことを学び、頼もしくなったな~と思います\(^o^)/
もう1人は6年目を迎える後輩です。
新卒で入職してきた彼女は、年齢の割には落ち着いていて、つかみどころのないふんわりした人でした。なので、最初の頃は「どんな人なんだろう」なんて思ってました(@_@??
でも、仕事を通して見えてきたのは「根性ある性格」の持ち主だということ。
とにかくめげない!逃げない!
この仕事をしているといろんな人に出会います。辛くあたられることもあります。悔しい思いもすることもあります。難しいケースに頭を抱えることもあります。
でも、彼女は良い意味で「鈍感」なのです。どんな事でも「とにかくやってみます!私は気にしません」と根性で乗り越えます\(^o^)/
そんな彼女は6年目を迎えて、気配りのできる素敵女子に成長しました!
そして、何より「面白さ」が加わり、時折繰り出されるナイスなコメントに「うまいなぁ!!」と感嘆させられることが増えました(^_-)-☆
そんな後輩たちの成長を感じながら、「人って日々成長するんだなぁ」としみじみ思います。
私も後輩たちに負けないように、日々人間性を磨いていきたいと思います\(^o^)/